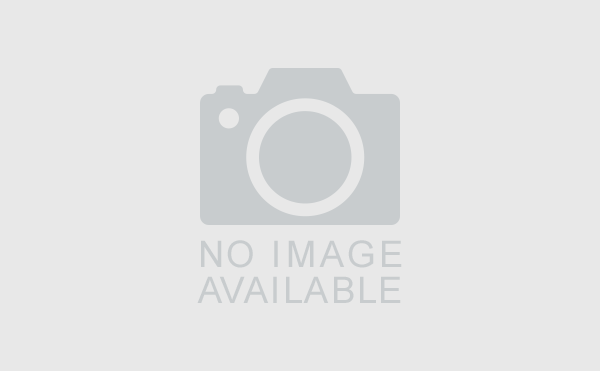賃金等請求権の消滅時効のあり方を検討
厚生労働省は、労働基準法による賃金などの請求権の消滅時効について検討する「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」(座長・岩村正彦東京大学法学部教授)を設置した。これは、昨年成立した改正民法により、一般債権の消滅時効の期間が5年ないし10年に統一されたことに伴うもの。労働基準法では、民法で定める消滅時効の特例として、賃金等の請求権の消滅時効期間を2年(退職手当は5年)と規定している。検討会は、関係団体からのヒアリングなども行い、今年の夏ごろに取りまとめを行う予定。
現行の民法では、債権の消滅時効を10年と定めている(第167条)。また、これとは別に、短期消滅時効として、月給や日給のように月単位以下で決めた使用人の給料については1年とするなどの規定を設けている(第174条など)。
ただし、これには他の法律で多くの例外が規定されており、その1つとして、労働基準法第115条の時効の規定がある。同条は、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」と規定している。
この特例が設けられた根拠は、労働者にとって重要である賃金などの請求権の消滅時効が1年ではその保護に欠け、一方、10年では使用者には酷に過ぎ、取引安全に及ぼす影響も少なくないためとされている。
そして、昨年の通常国会で、消滅時効の期間の統一化や短期消滅時効を廃止するなどの改正民法が成立した(施行は平成32年4月1日)。改正法では、一般債権の消滅時効は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(新設)、②権利を行使することができる時から10年間──とされ、また、職業別の短期消滅時効は廃止する整理が行われた。併せて、消滅時効に関する民法の規定の例外規定を持つ他の法律について、一括改正する法整備が行われた。しかし、この一括改正の中に労働基準法第115条は含まれていない。
このため、同省では、今回の民法改正に伴い、労働基準法による消滅時効のあり方を検討するため、学識経験者らによる検討会をスタートさせた。
同法第115条の対象となる請求権には、賃金(割増賃金を含む)のほか、休業手当、解雇予告手当、帰郷旅費などの金銭給付請求権のほかに、年次有給休暇請求権、退職時の証明も含まれる。検討会では、今後、関係団体等からヒアリングを行った上でこれらの請求権のあり方について検討を進めることとしている。特に、年次有給休暇請求権に関しては、消滅時効を延長すると年休の取得抑制につながる恐れがあると考えられることから、賃金等の金銭給付請求権と区別して検討することにしている。
検討会は、今年の夏を目途に検討結果を取りまとめる予定であり、その後、それを踏まえて労働政策審議会でさらに議論を深め、法第115条の見直しが提起された場合は、改正法案を来年の国会に提出することが見込まれる。