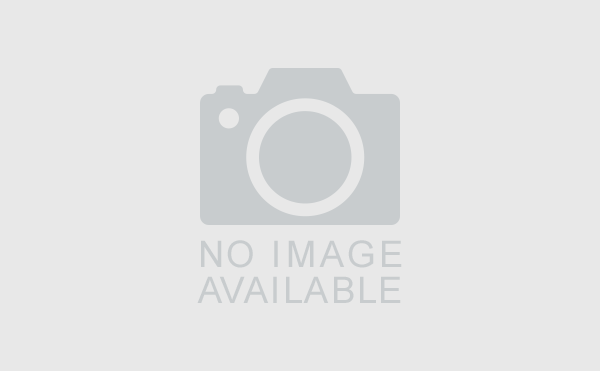訪問系サービス実施には事業者が一定の研修実施
外国人介護労働者の受け入れに関して、EPA介護福祉士の就労範囲に訪問系サービスを追加するに当たって講じる措置の内容について、今年8月から検討を行っていた厚生労働省の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」(座長・根本嘉昭神奈川県立保健福祉大学名誉教授)が報告書をまとめた。
平成26年10月に設置された同検討会は、これまでに、技能実習制度への介護職種の追加、EPA介護福祉士候補者等の更なる活躍促進策などについて検討し、その結果を取りまとめている。今年3月の報告書では、EPA介護福祉士候補者の受入れ対象施設の範囲の拡大、EPA介護福祉士の就労範囲の拡大などを提案した。ただし、現在は認められていない訪問系サービスを就労範囲に認めるに当たっての必要な対応については、様々な意見があったため、同検討会で引き続き議論することとされた。
今回の報告書では、EPA介護福祉士の就労範囲に訪問系サービスを追加するに当たって講ずべき必要な対応として、(1)既存の制度を踏まえた追加的に必要な対応(介護事業者が行うもの)、(2)EPAの枠組みを活用した対応(EPAに基づく介護福祉士候補者等の受入れにおける日本国内で唯一の受入れ調整機関である公益社団法人国際厚生事業団が行うもの)を示している。
事業者等が行うものの主な内容は、EPA介護福祉士が訪問系サービスに就労する場合に想定される「日本の生活に合わせたサービス提供」、「緊急事態発生時の対応」、「訪問サービス提供に関する適切な記録等の作成」の3つの課題への対応を挙げている。
具体的には、日本の生活に合わせたサービスの提供に関しては、①訪問介護の基本事項(心得・倫理、プライバシーの保護等)、②生活支援技術(高齢期の食生活、住生活、調理、掃除、ゴミ出し等)、③利用者、家族や近隣とのコミュニケーション、④日本の生活様式(文化・風習・習慣、年中行事等)──などを含む研修を行うことを求めている。
また、緊急事態発生時の対応に関しては、①緊急時の対応(緊急時の連絡先・その手段(携帯電話の貸与等)・連絡体制の確認、応急処置・救急車の要請などの急変時の対応)、②事故発生時の対応(利用者宅における物損事故、移動中の事故等への対応等)、③感染症への対応(感染予防、嘔吐物の処理等)、④リスクマネジメント(ヒヤリ・ハット事例等)──などを含む緊急時の対応マニュアルを整備するとともに、EPA介護福祉士への研修を行うことを求めている。
訪問サービス提供に関する適切な記録等の作成に関しては、チェックシート方式による簡略化など、記録や報告事項の記載方法について工夫することを挙げている。
同省では、報告書が挙げた対応策を留意事項として示した通知の発出、告示の改正などを行い、平成29年度には新制度に移行することを目指す方針。