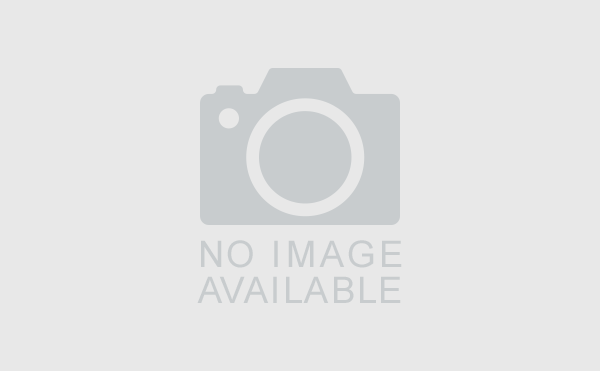三六協定の内容・残業の実態把握中心に議論
厚生労働省は、時間外労働の上限規制の検討に関し、時間外労働の実態把握を中心に検討する「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」(座長・今野浩一郎学習院大学経済学部経営学科教授)を設置し、第1回会合を先月9日に開催した。検討会では、労働基準法上の三六協定における時間外労働規制のあり方を検討することになっている政府の「働き方改革実現会議」の議論に資するよう、三六協定上の延長時間・実際の時間外労働実績などの実態や課題の把握をメインテーマに議論することになっている。
我が国の労働基準法では、労働時間の最長限度を「1週間40時間、1日8時間」と規定している(法第32条)。ただし、あらかじめ労使協定(通称・三六協定)を締結して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、協定した延長時間までの労働を可能とする仕組みとなっている(法第36条)。なお、協定により延長できる労働時間については、1ヵ月45時間、1年間360時間などの上限が告示で定められているが(限度基準告示)、その上限時間を超えて時間外労働をさせなければならない特別の事情が生じたときには、一定の事項を協定すれば限度基準を超えた時間外労働が可能となっている。そして、特別の事情が生じたときの延長時間には上限の定めはない。
日本と欧米諸国の労働時間を比較すると、1週当たりの労働時間が49時間以上の者の割合は、日本21.3%、アメリカ16.4%、イギリス12.5%、フランス10.4%、ドイツ10.1%──となっており、日本は長時間労働者の割合が特に高い(日本は総務省「労働力調査」、欧米諸国はILO「ILOSTAT Database」による。アメリカのみ2013年、他は2014年)。また、年平均労働時間は、日本1729時間、アメリカ1789時間、イギリス1677時間、フランス1473時間、ドイツ1371時間となっている(資料出所:労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2016」。いずれも2014年)。
時間外労働の上限規制の導入に関しては、今後の労働時間法制のあり方について平成25年9月から27年2月まで約1年5ヵ月にわたって議論を行った労働政策審議会の労働条件分科会で検討事項の1つとなっていたが、結論を得るに至らなかった。
その後、今年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「労働基準法については、労使で合意すれば上限なく時間外労働が認められる、いわゆる36(サブロク)協定における時間外労働の在り方について、再検討を開始する」とされた。政府は、これに基づき「働き方改革実現会議」を設置し、来年3月までに結論を出す方向で検討を開始することになっている。
厚生労働省の検討会では、「働き方改革実現会議」の議論に資するよう、①三六協定上の延長持間、実際の時間外労働実績などの実態や課題の把握、②諸外国における労働時間制度の現状と運用状況、③健康で仕事と生活の調和がとれた働き方を実現するための方策──を中心に検討することとしている。